左コーレス骨折(Colles骨折)後、保存療法だと2ヶ月程度でADLが可能になると言われています。
今回は骨折から2ヶ月以上しても発赤・熱感・疼痛・腫脹という炎症の4徴候(機能障害も入れると5徴候)が改善しないというケースからの学びです。
患者さんの状況
80代女性で受傷後ギプス固定・シーネ固定も取れたのに、一向に炎症が治らず、夜もジンジンして眠れないという方がいらっしゃいました。
2ヶ月間夜痛みで眠れないというのはかなり辛い生活ですね💦
まともに眠れていない状況では転倒リスクも高まってしまいます。まず早く眠れるようになって頂きたいところです。
レントゲン上の癒合はそれほど問題ないとのことでした。
臨床推論のプロセス
左前腕周囲のリハビリを受けておられたとのことなので、本来であれば2ヶ月も経過していればかなり回復しているだけの時間は経過しています。
なのに現実は回復が進んでいない・・・。
ではなにが回復を邪魔しているのか?
を検査する必要があると考えました。
評価と介入
全身をチェックすると、鞍隔膜、小脳テント、後頭下隔膜、胸郭上口の制限が著明に存在する状況でした。
これらは頭蓋〜頸部〜肩甲帯〜胸郭にわたって連続している構造です。
ひょっとしたらと思い聞いてみると、頭も少し打ったとのことでした。
リハビリをされていたおかげで上肢帯には著明な制限は認められませんでした。
上記の構造に対してリリースをかけると、直後から左上肢帯に夜間に起きたようなジンジンとした痛みが出るとの訴え。
反応をみて許容範囲内であることを確認しながら10分ほどでリリース完了。
結果
その直後より徴候は改善してきて翌日にはさらに軽減。
夜間もよく眠れたとのことでした😄
まとめ
転倒した際には「前腕の骨が折れる」ということだけではなく、
- 本人も述べたように他の部位も打っていた
- 衝撃が他の部位に分散した
- 受傷前から持っていた問題が回復を阻害した
いずれかの要因があるかと思います。
疾患に対する介入はもちろん大切ですが、「回復する身体機能」という視点でみた時には視点を広げる必要があるということを実際に体験させていただきました。
このような全身評価の視点が参考になれば幸いです。
2025年12月14日に全身の循環から捉えるという視点に役立つための勉強会を開催予定です。
興味のある方はこちらをご覧ください。
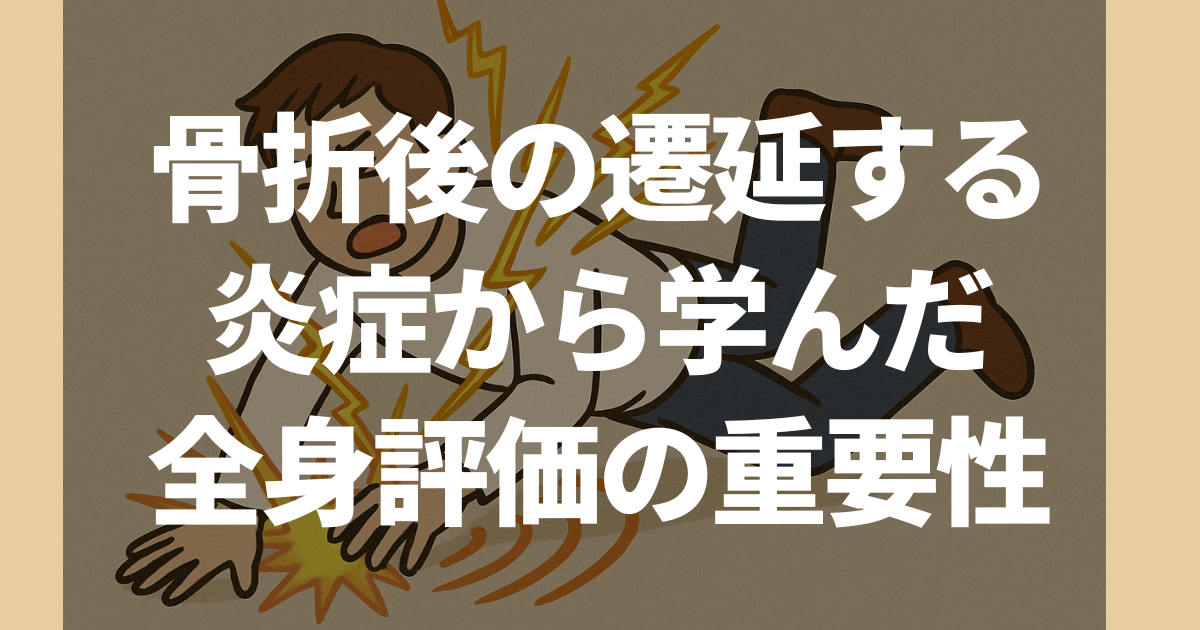
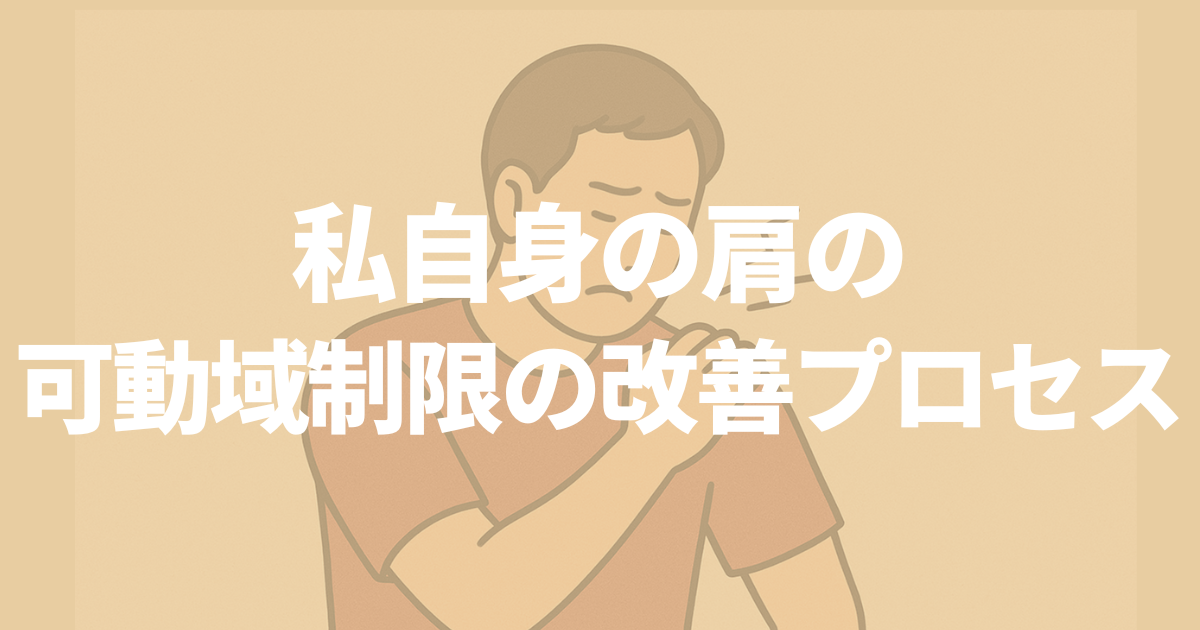
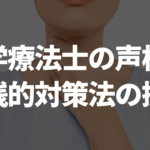


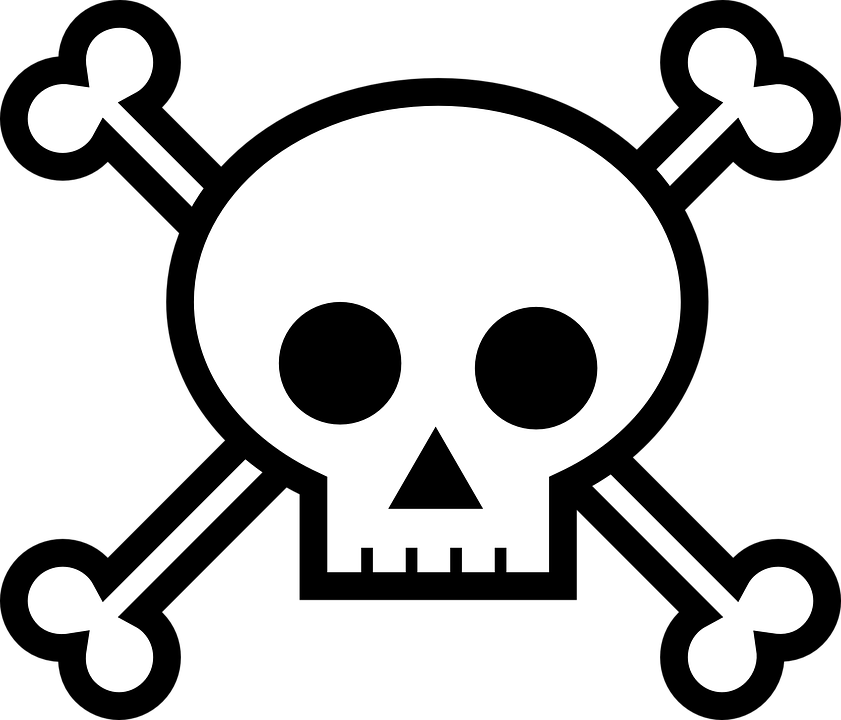
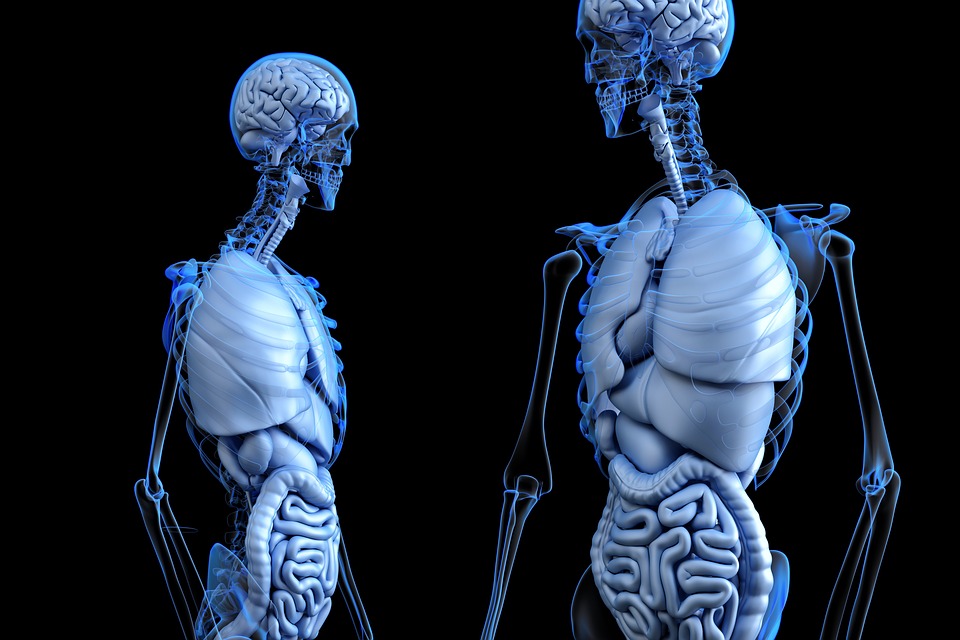
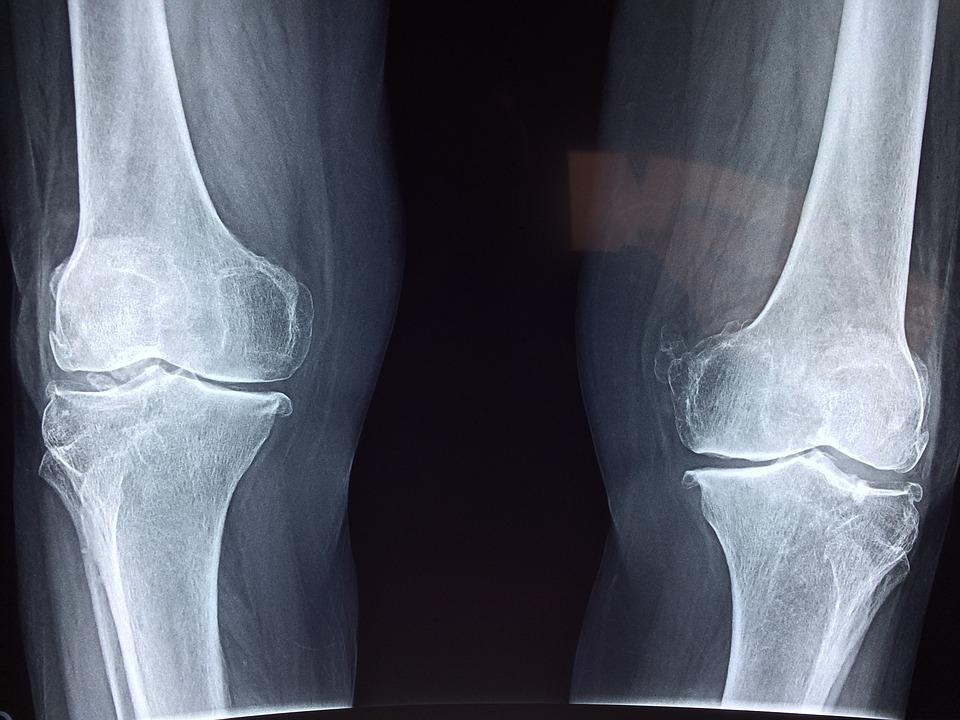
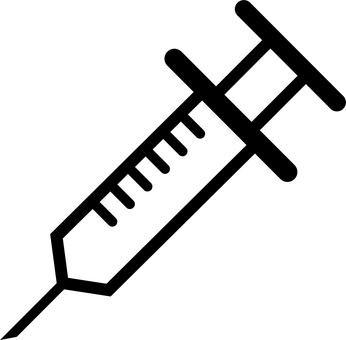



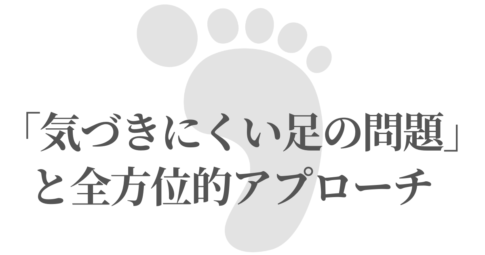
コメントを残す