人間の健康を捉える上で、「ボディ・マインド・スピリット」の三位一体という視点があります。
ホリスティック医学の視点であり、オステオパシー創始者のスティル医師もこの視点から人の健康を捉えていたそうです。
この記事では、理学療法士としてこの視点を臨床応用するために考察しています。
1. ボディ・マインド・スピリットの基本概念
- ボディ(体):物質としての存在する身体構造
- マインド(心):思考、感情などの心理面
- スピリット(精神):マインドより深い意味での精神的な充実度、関係性や存在意義などの社会面
「これら3つが相互に関係し合い、バランスが取れている時に真の健康が実現される」
とされています。
1947年WHO憲章の【健康の定義】は
「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます」
とされていますので、両者の視点は遠からずといった感じでしょうか。
個人的な体験例として
- マインドがボディに影響
白衣高血圧
マラソンでの限界を感じても応援されたらまだ振り絞れる感覚
笑顔になるとパフォーマンスがあがるなど - スピリットがボディに影響
夫婦関係性の不全から腰部脊柱管狭窄症と診断される症状を引き起こした事例 - ボディがマインドやスピリットに影響
風邪を引くと弱気になる。
仕事を休むことで職務を果たせずより辛くなる。
2. 現代医療における「ボディ」中心主義
西洋医学は主に身体(ボディ)にフォーカスした診断・治療アプローチを重視してきました。
なぜなら「目にみえる」もしくは「数値化できる」からです。
だからこそエビデンスが積み重なり、再現性の高い素晴らしい治療が構築できるからです。
特に医師は直接命に関わるが故に、
ボディへのフォーカスはより厳格なものになっていると感じます。
この視点無くして素晴らしい命を救える医学が発展してなかったと思います。
この恩恵には個人的にも感謝してもしきれません。
一方、一概には言えませんが、
患者さんがパソコン上のデータとして扱われる傾向があるのも事実です。
医師の対応を見ていると、
「その領域は関与する領域ではない」
「できる部分にフォーカスする」
という印象に映ることもあるのではないでしょうか?
専門分野外に軽々しく触れないというのは、慎重で尊いものだとも思います。
では理学療法士としてはどうでしょうか?
3. 理学療法士としての立ち位置
理学療法士は患者と長時間関わるため、
細かく患者の状態を観察・評価できる特権的立場にあります。
この立場で仕事をしていると介入する領域の幅は、必然的に広がることを感じている方も多いのではないでしょうか?
- ボディへのアプローチ:
運動療法、物理療法など身体機能への直接的介入 - マインドへのアプローチ:
患者の心理・思考に寄り添い、モチベーションを高める関わり - スピリットへのアプローチ:
生きる意味や目的を尊重し、QOL向上を目指す支援
エビデンスのあるアプローチをボディに提供すると同時に、三位一体の視点を持ち合わせておくことは非常に重要なのかと思います。
1982年の国連によるリハビリテーションの定義にマッチするかと思います。
「身体的、精神的、かつまた社会的に最も適した機能水準の達成を可能とすることによって、各個人が自らの人生を変革していくための手段を提供していくことを目指し、かつ時間を限定したプロセスである。」
実際にBPS(Biopsychosocial)モデルという心理社会的要因と腰痛の関連についての報告も上がっています。
参考:
労災疾病等医学研究普及サイト:職場での腰痛には心理・社会的要因も関与している ─職場における非特異的腰痛の対策─
4. 臨床実践における課題と現実
三位一体へのアプローチ(方法論)には再現性を証明しようとするには限界があると感じています。
ボディ(身体)の評価要素
- 身体(痛み、緊張、可動域制限、重さ、姿勢・動作、反射など)
- 口腔・栄養(体重、口腔状態、嚥下など)
- 自律神経症状の確認(睡眠、排尿・排便、反射)
などの評価をすると思いますが、
診断名・症状が同じでも問題部分は一人一人全く違うのが現実です。
そして世にある様々なアプローチ方法論においても未だ完璧なものはないのが現実です。
マインド(心)の評価要素
- 精神的健康状態(不安、うつ症状など)
- 思考パターン(症状への認識や解釈など)
- 感情の状態と処理能力
スピリット(精神/魂)の評価要素
- 人生の目的意識
- 価値観と実際の生活の一致度(「理想」と「現実・言動」の一致)
- 平和感や充足感
マインド・スピリットはボディよりもさらに一人一人の違いが顕著なものです。
また理学療法士はこの部分に対しての理解・教育がとても弱いと感じています。
時に患者さんに「正論」を押し付けてしまうこともあるかもしれません。
実際には個別性を踏まえて相手の主体性を尊重し、トライアンドエラーを繰り返していく事が現実的な方法かと思っています。
5. 凡人セラピストとしての臨床哲学
私は理学療法士の資格取得後、ゴリゴリに文献を読み漁り、心と身体は関係しているのはざっくりと理論・理屈程度で理解していたつもりでした。
しかし古武術の稽古を9年程続ける中で、
心のあり方が身体にとても大きな影響を及ぼすことを身を持って知りました。
この経験を経て、それまでのボディ中心のアプローチに疑問を持ち、さらに脳科学や心理療法などに触れる中で結果としてボディ・マインド・スピリットも含めた視点を大切にするようになりました。
その中で大切にしていることは下記になります。
- 医師とは異なる視点を持つことの意義:
医師の診断・指示を踏まえつつボディ・マインド・スピリットの視点のように広い視点から患者さんと関わる。
もう少し具体的にいうと、
- 科学的エビデンスを尊重しつつも、患者の個別性を見失わない姿勢:
方法論に限界を認識しながらも放棄はせず、患者さんの反応第一に関わる。 - 患者中心のアプローチ:
患者の価値観や目標を中心に据えた、ボディの理論を押し付けないサービス提供
6. 具体的取り組み方の提案
忙しい臨床現場でも実践できるおすすめをお伝えしたいと思います。
最近よく私が使っている言葉なのですが、
- 「今どのように感じてらっしゃいますか?」
- 「その様に感じておられるんですね」
- 「そう思われるのも無理ないですね」
というものです。
意図は色々あるのですが、重要なポイントは専門的知識を持って患者さんの言っていることが合っているか間違っているかの判断はしないということです。
- 意識を変えると、行動が変わる
またその逆で - 行動を変えると、意識も変わります。
例え微塵も思ってもなくても言ってみて下さい(笑)
特に
「患者さんの気持ちが全然わからない」
「なんて怠惰なんだ」
など否定的に感じてしまっている状態であれば、ひょっとしたら想定以上の変化をご自身にもたらしてくれるかもしれません。
まずは使ってみてご自身の変化を教えてもらえると嬉しいです。
7. まとめ:理学療法士としてのボディ・マインド・スピリットの統合
- 患者に真に貢献するためには、三つ全てをアプローチ対象として捉える姿勢が不可欠
- 理学療法士として専門性は決して無駄にならない。ただし限界があることを踏まえる。
あなたはどのようにボディ・マインド・スピリットについて向き合っていますか? ご意見を頂けると幸いです。
ご覧いただきありがとうございました!
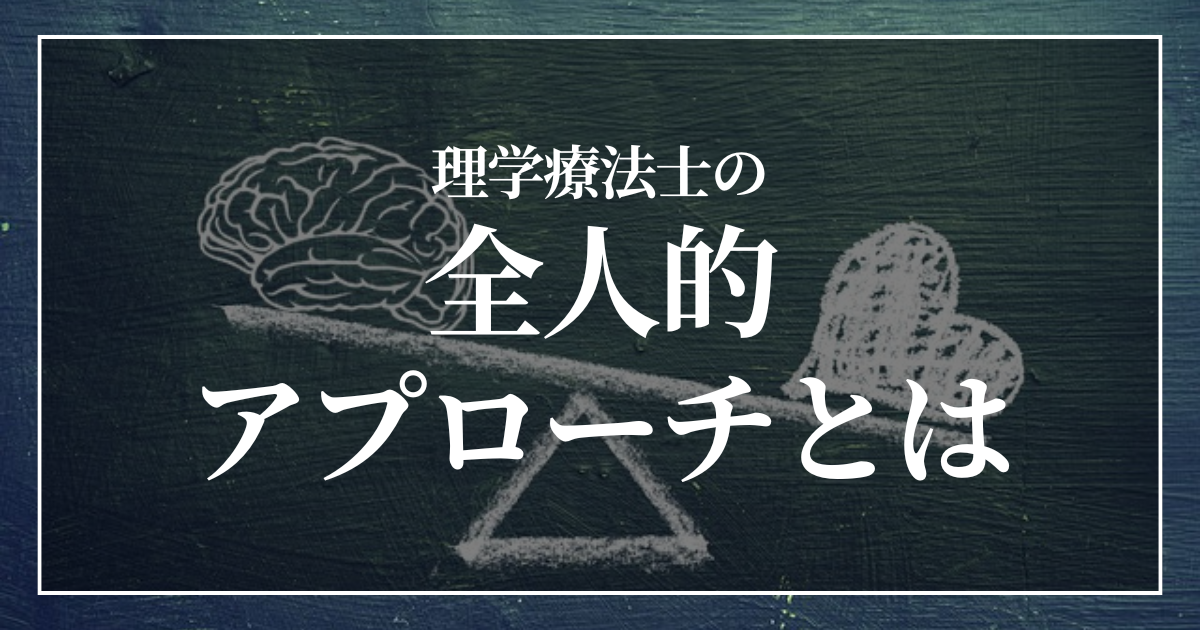

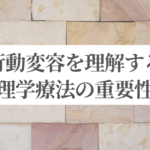
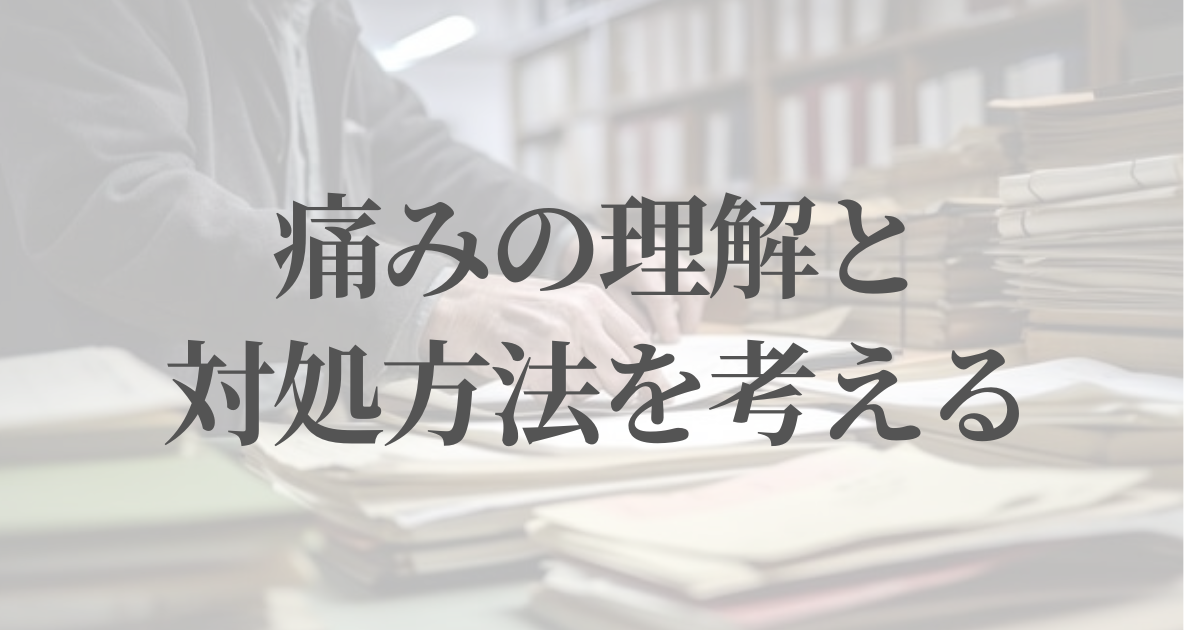
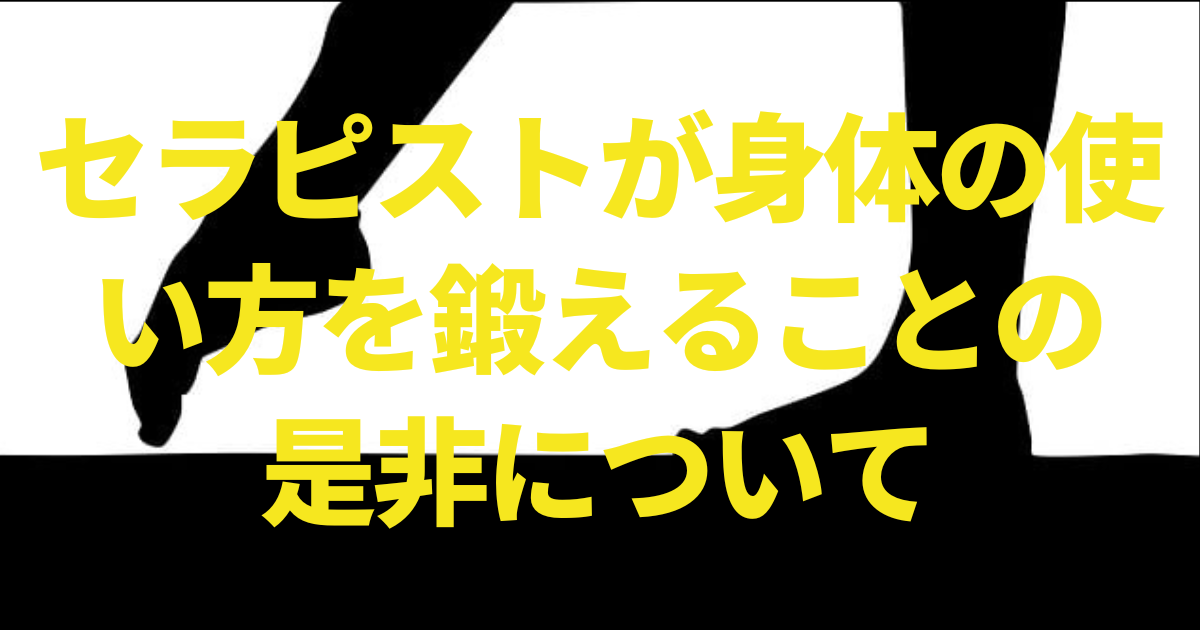
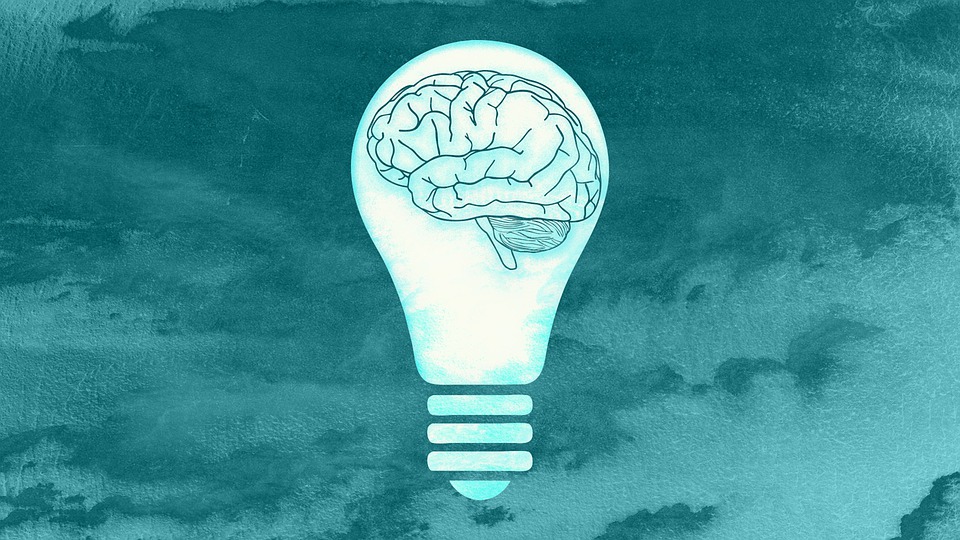
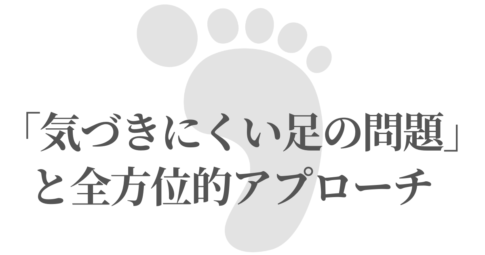
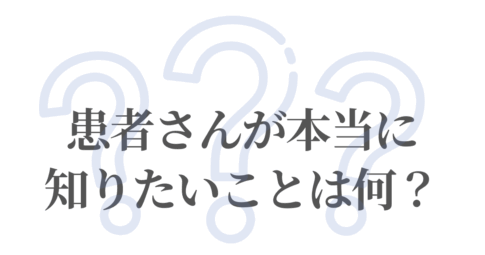

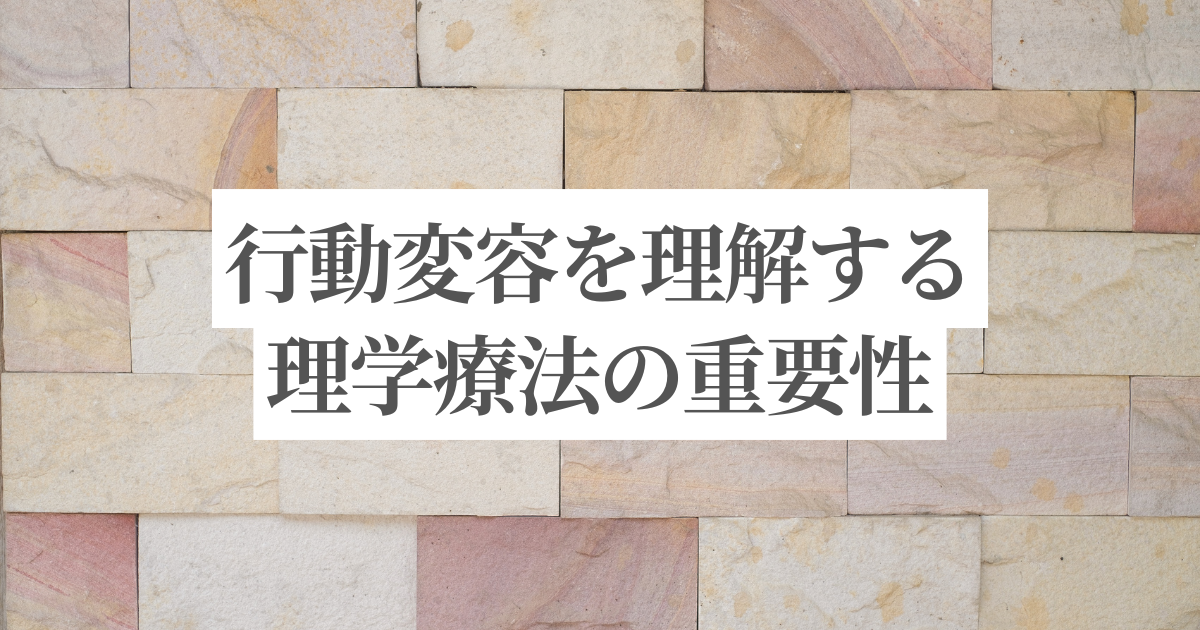

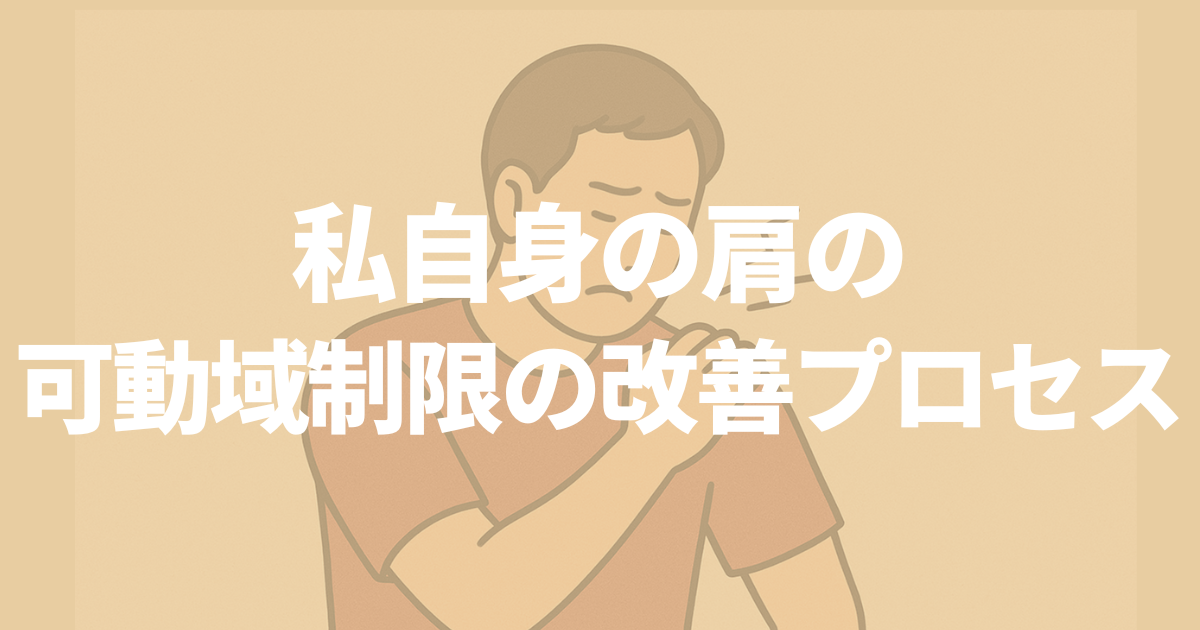
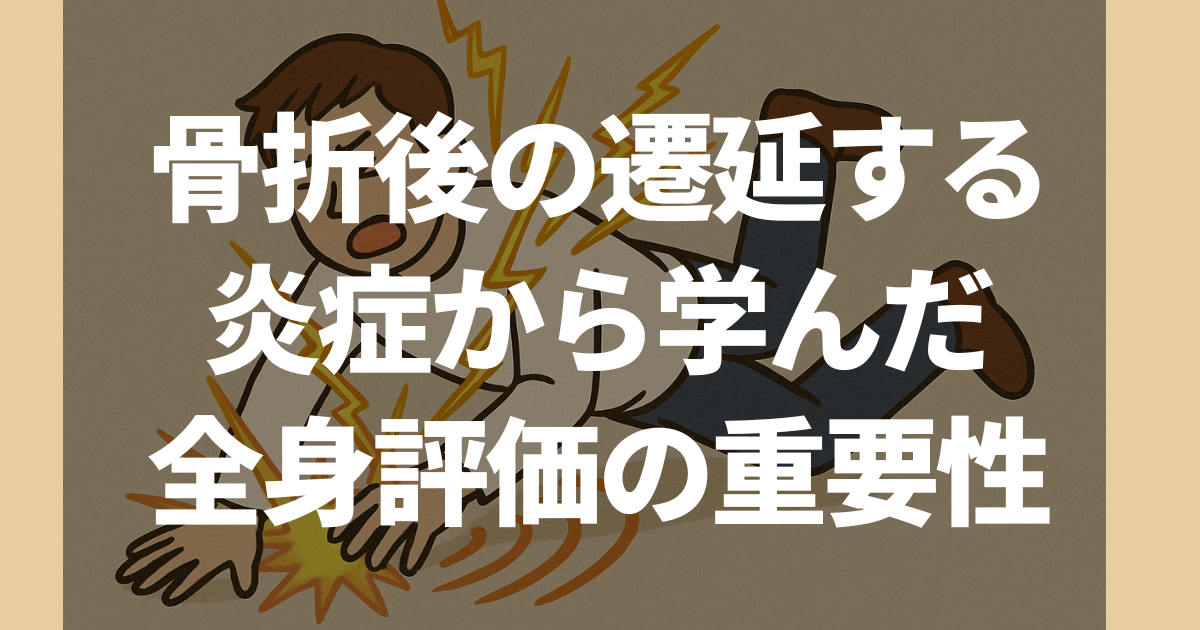

コメントを残す