はじめに
「実行期まで到達すれば行動変容が成立した」—こうした認識が理学療法の臨床現場で散見されますが、これは本当に正しいのでしょうか?
トランスセオレティカルモデル(TTM)は健康行動変容を支援する理論として広く活用されていますが、特に「実行期」の位置づけについては誤解も多いようです。
本記事では、TTMの理論的枠組みと実証研究データに基づき、実行期の真の意味と臨床での適切な支援方法について考察します。
TTMモデルの基本構造と実行期の位置付け
TTMモデルでは行動変容を次の5つの段階に分類しています:
- 無関心期(行動変容の意図がない)
- 関心期(行動変容の意図はあるが、まだ準備ができていない)
- 準備期(行動変容の準備ができている)
- 実行期(行動変容を実際に開始している)
- 維持期(行動変容が習慣化している)
実行期は、行動開始から6ヶ月未満の期間を指し、行動変容の初期段階として位置付けられます。この段階では患者さんが具体的な行動変化を開始した状態ですが、厚生労働省のガイドラインでは「行動が定着するまでに少なくとも6ヶ月の維持期間が必要」と明記されています。
実行期の心理的特性:不安定さを理解する
実行期にある患者さんには以下のような心理的特性が見られます:
1. 変容の両価性
新しい行動のメリットを実感しつつも、同時に生活習慣の変更に伴うストレスも経験しています。例えば、毎日の運動でだるさを感じながらも、体調の改善も少しずつ実感している状態です。
2. 自己効力感の不安定化
「この調子で続けられるだろうか」「うまくいくだろうか」と、新たな行動パターンの持続可能性に対する自信が揺らぎやすい時期です。
3. 環境適応の課題
兵庫県の保健指導データによれば、従来の生活環境との調和に困難を抱えるケースが43%に上ります。「職場の飲み会が多くて食事制限が難しい」「家事や育児で運動の時間が取れない」といった環境要因が大きく影響します。
データで見る実行期の現実
大規模コホート研究(n=178,780)の結果から、実行期の変容の不安定さが明らかになっています:
- 維持期への移行率:58.2%(成功例)
- 準備期への後退率:22.7%
- 無関心期への完全後退率:9.1%
- その他(脱落等):10.0%
つまり、実行期に到達した人の約42%は、6ヶ月後には行動変容を維持できていないことになります。
特筆すべきは、社会的サポートが不十分な環境では後退リスクが3倍増加するという点です。私たち理学療法士による適切なサポートがいかに重要かを示す結果と言えるでしょう。
健康指標から見た実行期と維持期の違い
実行期から維持期への移行の重要性は、健康指標の変化からも確認できます:
- 新規CKD(慢性腎臓病)発症リスク:
- 維持期移行者:0.82(95%CI 0.79-0.85)
- 実行期から後退した者:1.15(95%CI 1.09-1.21)
この数字が示すのは、実行期から維持期に移行できた人は腎機能低下リスクが18%減少する一方、実行期から後退した人はリスクが15%上昇するという事実です。行動変容の「持続」こそが健康改善の鍵を握っているのです。
実行期支援の実践的課題
理学療法士として実行期の患者さんを支援する際、以下の課題を認識しておく必要があります:
1. 逆戻りメカニズムの複雑性
認知的不協和理論に基づく葛藤状態が平均3.2ヶ月持続します。「運動しているのに思ったほど効果が出ない」「頑張っているのに周りからの評価が変わらない」といった葛藤が行動継続を妨げる要因となります。
2. 環境要因の影響度
神戸大学医療人材育成センターの調査によれば、職場環境や家庭環境が行動継続を阻害するケースが67%に及びます。環境調整や周囲の理解促進も支援の重要な一部です。
3. 報酬系の遅延効果
行動変容の利益実感までに平均4.2ヶ月を要します。「すぐに効果が出ない」ことへの対応として、小さな成功体験を積み重ねる工夫が必要です。
保健指導従事者の声:最も難しいのは実行期支援
興味深いことに、同調査では保健指導従事者の82%が「実行期支援が最も困難」と回答しています。その理由として:
- 患者の変化に合わせた柔軟な対応が必要
- 継続的なモニタリングと適切なフィードバックのタイミングの難しさ
- 環境要因への介入が限定的
などが挙げられています。
理論的観点からの再検証
TTMの原典であるプロチャスカの研究では、行動変容を「開始」と「維持」の2段階に大別し、実行期を「行動開始後の不安定期」と定義しています。
また、Oxford Academicが発表したシステマティックレビュー(2020)では、実行期単独での行動変容持続率が35%以下であることを指摘し、「維持期への移行が真の変容指標」と結論付けています。
理学療法実践への提言:実行期から維持期へ
以上のデータと理論を踏まえ、理学療法の臨床実践において以下のポイントを意識することが重要です:
1. 実行期は「完了」ではなく「過程」
実行期に入ったからといって「もう大丈夫」と考えるのではなく、維持期への移行を促す継続的なサポートが必要です。
2. 環境調整の重視
患者さんの生活環境や周囲のサポート状況を評価し、必要に応じて家族や職場への働きかけも検討しましょう。
3. 小さな成功体験の積み立て
すぐに大きな効果が見えにくい時期だからこそ、小さな進歩や変化を患者さんと共有し、自己効力感を高める関わりが重要です。
4. 定期的なフォローアップ
実行期から維持期への移行を支援するため、適切な間隔でのフォローアップを設定しましょう。
5. 再発防止策の事前準備
「うまくいかない時」の対処法を事前に患者さんと話し合っておくことで、完全な後退を防ぐことができます。
まとめ:行動変容の真の成立とは
現行のエビデンスを総合すると、TTMモデルにおいて実行期は行動変容の重要な転換点ではあるものの、単独で変容成立を保証する段階ではありません。行動変容の真の成立には、実行期から維持期への円滑な移行が必須です。
臨床現場では「実行期に入ったから支援終了」ではなく、「実行期から維持期への移行をいかに支援するか」という視点が求められています。これこそが、私たち理学療法士が患者さんの真の回復と自立を支える鍵となるのではないでしょうか。
「行動変容を理解する理学療法の重要性」という記事にて詳しく解説しています。実践的なコミュニケーション技術やケーススタディを交えながら、より具体的な支援方法を紹介していきます。
ご質問やご意見があれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。

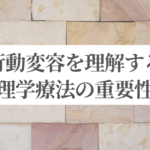






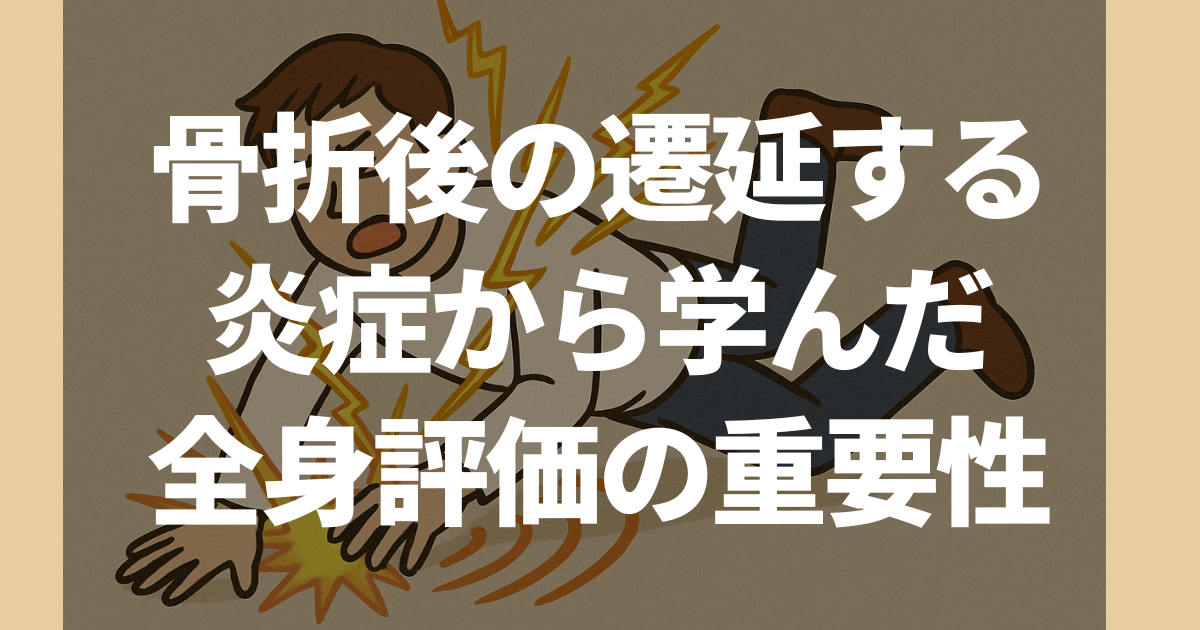
コメントを残す